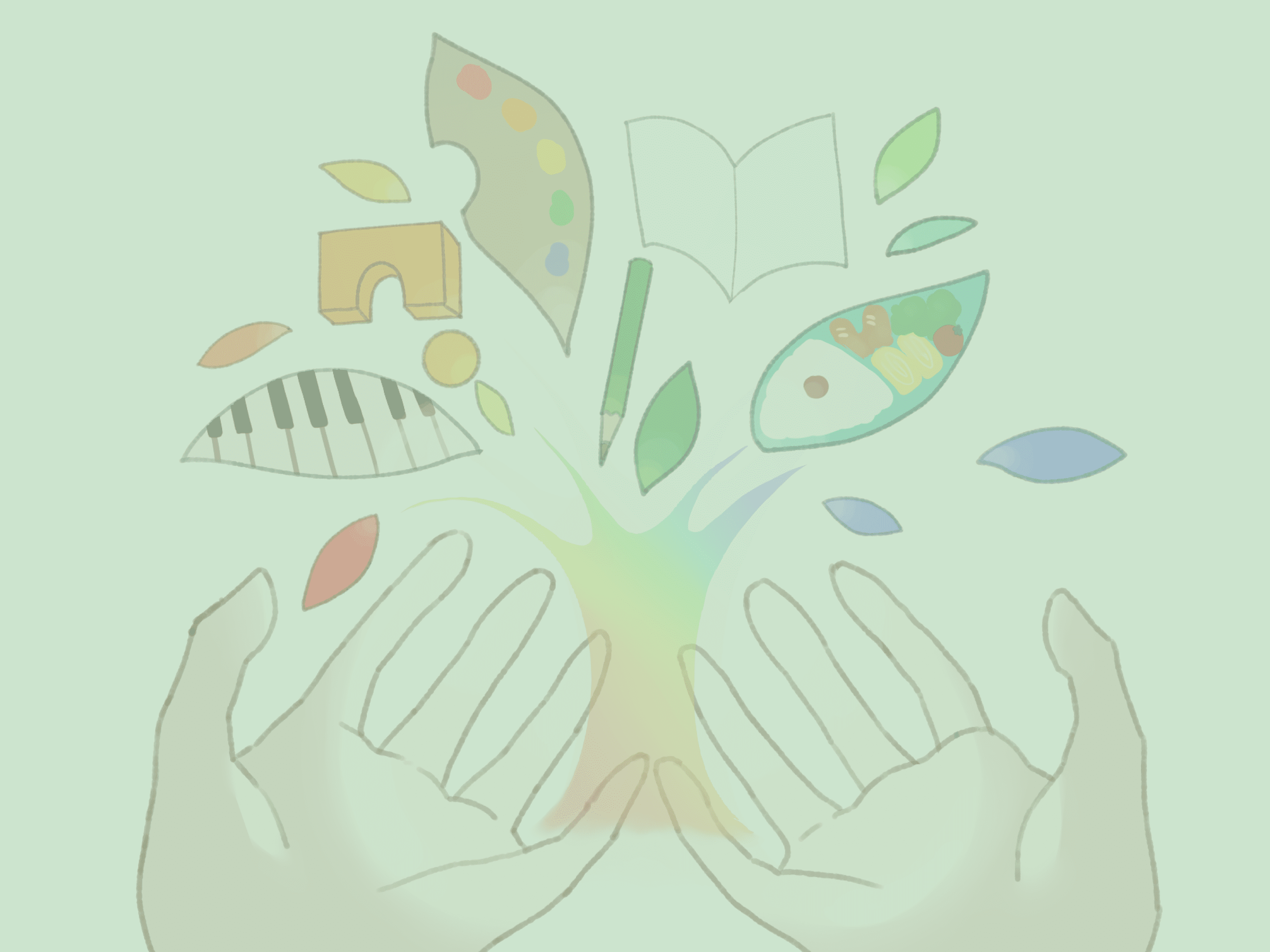【清水研究室 卒業研究】
清水研究室では、小学校教科教育の授業デザインについて研究しています。またその一環として防災教育も学んでいます。ゼミ旅行では毎年、東日本大震災の被災地を訪問し、学びを深めています。
訪問する被災地は南三陸町と石巻市ですが、途中、気仙沼駅に立ち寄りました。「東北の子どもたちに笑顔を届けたい」との思いから、東北復興支援企画として、ピカチュウがたくさん描かれた電車が走り、駅にはキャラクターが設置されていました。
気仙沼駅からはバス高速輸送システム(BRT)のバスに乗車しました。震災で不通になった区間に導入され、運行本数も増えたとのことで、復興が着実に進んでいることを学びました。

南三陸町では、南三陸町震災復興記念公園を見学しました。この公園は現在の避難場所となっているとともに、震災の記憶と教訓を次世代へ伝える場所として整備され、追悼と継承の場になっています。公園の高台には箱形のベンチがあり、中には災害時に必要な食料や毛布、テントなどが収納されていました。

石巻市では大川小学校を訪問し、「大川伝承の会」の方から震災時の様子をうかがいました。震災では震度6強の強い揺れを観測し、押し寄せた津波が北上川を逆流して甚大な被害が起こったこと、朝元気に登校していった子どもたちの多くが亡くなったことを聞きました。また、震災遺構となった大川小学校を案内していただき、日々の子どもたちの生活の様子についても話していただきました。日頃の防災教育の大切さ、教員として子どもの命を守ることの重要さを改めて学びました。


【被災地を訪問した学生の学び】
〇震災被災地では「命を守るための防災教育」について考えさせられました。児童の大切な命を守るために、私たちにできる教育を追求していきたいです。
〇被災地の見学では、実際に現地を見ながらお話を聞くことができ、実際に行かなければ分からなかった現場の空気を感じることができました。
〇震災被災地では、実際に経験した方からお話を聞くことができ、防災について考えさせられました。この2日間で多くのことが学べました。
〇子どもたちを守るという視点から教師について考えることができました。もしも震災が起こったらどうするべきか、事前の考えや行動力が命を守る第一歩であることに気付くことができました。
〇防災訓練や備えの大切さを改めて感じることができました。日頃から逃げる災害に備えることの大切さを学びました。
〇子どもたちを守る教員の判断や防災意識を高めることが、私たちにできる備えであることを学びました。4月から子どもの命を守る立場になります。子どもたちを守る責任や重大さを感じ、貴重な学びに繋がりました。
〇災害が起きた時の対応の仕方や被害を最小限に抑える方法などを学びました。実際に現地で被害の状況を目の当たりにすることで、自分事として考えることができました。被災地での学びをこれから受けもつ子どもたちへ伝えていきたいです。
〇地震や津波の怖さを改めて実感しました。被災された方のお話を聞く機会があり、学校で行っている避難訓練の重要性を肌で感じました。
〇震災被災地である大川小学校を訪れ、避難訓練や避難マニュアルの大切さを学ぶことができました。今年度から小学校教諭になります。災害時、その場での臨機応変な対応が大切であることを学びました。


ゼミ旅行では、大川小学校伝承の会の皆様をはじめ、たくさんの方々にお世話になりました。ありがとうございました。